1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
(1) 地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進
【施策番号150】
警察庁においては、市区町村における犯罪被害者等施策の窓口となる部局(以下「施策主管課」という。)の確定状況等について定期的に確認しており、平成28年度以降、全ての市区町村で施策主管課が確定している。また、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、市区町村において犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置を要請しており、全国1,721市区町村(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)について、31年4月現在、全ての市区町村において、総合的対応窓口が設置されている(基礎資料5-3参照)。都道府県・政令指定都市については、23年度以降、全地域において、総合的対応窓口が設置されている。
これら地方公共団体における総合的対応窓口のほか、都道府県・政令指定都市が行っている犯罪被害者等への支援施策等について、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi/madoguchi.html)に掲載し、国民に対する周知に努めている。
(2) 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進
【施策番号151】
警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、総合的対応窓口の機能の充実や政令指定都市の区役所における体制整備を要請している。
また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」に、地方公共団体における犯罪被害者支援担当者に対する研修会の実施状況やその内容等を掲載して発信することにより、各地方公共団体における総合的対応窓口の機能の充実の促進に努めている。
(3) 地方公共団体における専門職の活用及びこれらとの更なる連携・協力の充実・強化
【施策番号152】
警察庁においては、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、犯罪被害者支援分野における社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師等の専門職の活用を働き掛けるとともに、総合的対応窓口と関係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請している。
平成31年4月現在、13都道府県・政令指定都市、80市町村において、総合的対応窓口等に専門職を配置している。
(4) 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進
【施策番号153】
警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者支援に資するよう、犯罪被害者等に関する条例の制定及び計画・指針の策定状況について情報提供を行っている(警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」:https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/jorei/jorei.html)。
また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」では、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定を取り上げ、当該条例に基づく主な支援施策等を紹介しているほか、平成29年3月には、都道府県・政令指定都市における犯罪被害者等支援に特化した条例集を取りまとめるなど、地方公共団体に対する情報提供に努めている。
31年4月現在、63都道府県・政令指定都市、588市区町村において、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定が行われている。
(5) 地方公共団体間の連携・協力の促進等
【施策番号154】
警察庁においては、都道府県内における市町村の連携・協力の促進を図るため、都道府県による市町村の犯罪被害者支援担当者を集めた研修に講師等として職員を派遣しているほか、犯罪被害者等施策の総合的推進に関する事業として、平成30年度は、青森県、大阪府及び熊本県において、市町村職員等を対象にした研修会を実施した。
また、地方公共団体間の連携・協力が必要な事案が発生した場合に備えて、各地方公共団体における犯罪被害者支援に関するコンタクト・ポイントを一覧にまとめた資料を整備・配布し、地方公共団体間の情報の共有化を促進している。
(6) 地方公共団体における性犯罪被害者支援への取組の促進
【施策番号155】
【施策番号65】参照
(7) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供
【施策番号156】
【施策番号59】参照
(8) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用
【施策番号157】
【施策番号60】参照
(9) 性犯罪被害に遭った児童生徒への対応の充実
【施策番号158】
文部科学省においては、子供たちが全国どこからでも、いつでも、気軽に悩みを相談できる「24時間子供SOSダイヤル」を設置し、教育委員会等による紹介カードやリーフレット等の配布等を通じて、児童生徒や保護者への周知を図っている。
また、近年、若年層の多くが、SNSを主なコミュニケーション手段として用いている状況等を受け、平成30年から地方公共団体に対し、SNS等を活用した児童生徒向けの相談体制の構築を支援している。
(【施策番号55】参照)
(10) ワンストップ支援センターの設置促進
【施策番号159】
ア 【施策番号61】参照
【施策番号160】
イ 【施策番号62】参照
【施策番号161】
ウ 【施策番号63】参照
【施策番号162】
エ 【施策番号64】参照
【施策番号163】
オ 【施策番号65】参照
(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援
【施策番号164】
警察においては、公益社団法人全国被害者支援ネットワークをはじめとする犯罪被害者支援団体に対し、研修内容に関しての助言や講師派遣等の協力を行っている。また、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談や情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等、犯罪被害者等に対する支援全般を管理するコーディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援するため、民間支援員も参加できる研修を実施するとともに、被害者支援連絡協議会等で具体的事例を想定した犯罪被害者支援についての実践的なシミュレーション訓練を実施している(被害者支援連絡協議会については、【施策番号167】参照)。
(12) 地方公共団体の取組に対する支援
【施策番号165】
内閣府においては、配偶者暴力相談支援センターにおける相談対応の質を向上させるとともに、犯罪被害者支援を充実させるため、都道府県、市町村等の関係機関及び民間の更なる連携の促進を図ることを目的として、官民の配偶者暴力被害者支援の関係者(配偶者暴力相談支援センター長、地方公共団体の職員及び相談員)を対象としたワークショップ等を行う「女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進事業」を実施している。
(13) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
【施策番号166】
警察においては、他の犯罪被害者支援に関係する機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、これらの関係機関・団体等の犯罪被害者支援のための制度等を説明できるように努めている。また、犯罪被害者支援のための諸制度を所掌する省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、これを必要とする犯罪被害者等に提供することとしている。
(14) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進
【施策番号167】
警察においては、生活上の支援をはじめ、医療、公判に関すること等、極めて多岐にわたる犯罪被害者等のニーズに応え、総合的な支援を行うため、警察のほか、検察庁、弁護士会、法テラス、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局、県や市の相談機関や犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等による被害者支援連絡協議会を全都道府県に設立し、犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。
このほか、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな総合的支援を行うために、警察署等を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)を構築している。
平成30年4月現在、全ての都道府県において、被害者支援連絡協議会と1,131の被害者支援地域ネットワークが設置され、全ての地域を網羅している。
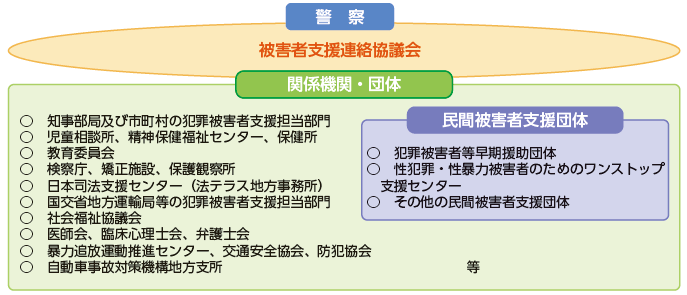
(15) 警察における相談体制の充実等
【施策番号168】
ア 警察においては、犯罪被害の未然防止に関する相談等の各種相談に応じる窓口を設置している。また、電話による相談についても、全国統一番号の警察相談専用電話「#9110」番を設置するとともに、このような総合的な相談に加え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪被害相談(【施策番号201】参照)、少年相談、消費者被害相談等の個別の相談窓口を設け、相談体制の充実に努めている。さらに、犯罪被害者等の住所地や匿名と実名の別を問わず相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望により、被害者支援連絡協議会等のネットワークに参画する関係機関・団体に関する情報提供やこれらへの引継ぎを行うなど、犯罪被害者等がより相談しやすく、より負担が少なくなるような対応に努めている。
加えて、警察庁から委託を受けた民間団体が、特定の犯罪等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う匿名通報事業を実施し、被疑者の検挙や犯罪被害者の早期保護等に役立てている(【施策番号78】参照)。
都道府県警察においては、交通事故被害者等に対して、「被害者の手引」、現場配布用リーフレット等を活用して、
- 刑事手続の流れ
- 交通事故によって生じた損害の賠償を求める手続
- ひき逃げ事件や相手方が自賠責保険に加入していなかった場合に国が損害の塡補を行う制度(政府保障事業)
- 被害者支援に関する各種相談窓口
等に関する説明を行っている。
また、都道府県警察においては、交通事故被害者等から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日等について問合せがあった場合や、交通死亡事故の遺族、重度後遺障害を受けた者及びその直近の家族から加害者に対する行政処分結果について問合せを受けた場合には、適切な情報の提供を行っている。平成30年中の都道府県警察における意見の聴取等の期日等に関する問合せに対する回答件数は3件、行政処分の結果に関する問合せに対する回答件数は23件であった。
都道府県交通安全活動推進センターにおいても、職員のほか、弁護士等が、交通事故被害者等からの相談に応じ、適切な助言を行っており、29年度中の同センターにおける交通事故相談回数は9,452回であった。
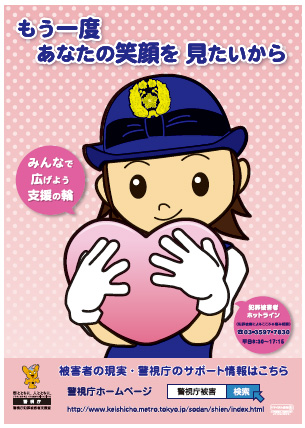
【施策番号169】
イ 警察においては、性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進するなどして、性犯罪被害相談において、相談者の希望する性別の職員が対応することができるように努めている。また、執務時間外においても当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進している。
(16) 警察における被害少年等が相談しやすい環境の整備
【施策番号170】
警察においては、全都道府県警察に設置されている少年サポートセンターや警察署の少年係等が窓口となって、少年や保護者等からの相談を受け付けている。相談には、警察官や少年補導職員が対応し、必要な助言、指導を行っている。

また、全都道府県警察に「ヤングテレホンコーナー」等の名称で電話による少年相談窓口を設けており、フリーダイヤルによる相談や電子メール等による夜間・休日における受付等、少年や保護者等が相談しやすい環境の整備を図っている。
平成30年4月現在、全国194か所に少年サポートセンターが設置されており、このうち73か所は、少年や保護者等が気軽に立ち寄ることができるよう、警察施設以外の施設に設置されている。
警察庁においては、相談内容に応じた適切な窓口を紹介するリーフレットを作成して都道府県警察や関係府省に配布している。
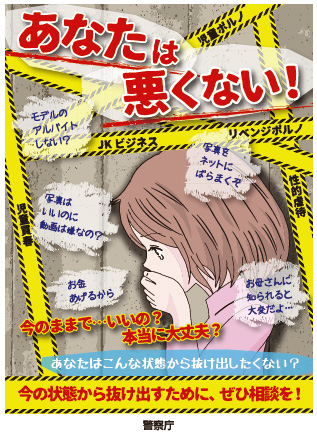

(17) 「指定被害者支援要員制度」の活用
【施策番号171】
警察においては、専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、あらかじめ指定された警察職員が事件発生直後から犯罪被害者等への付添い、情報提供等を行ったり、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介・引継ぎを行ったりする指定被害者支援要員制度を各都道府県警察で運用している。また、指定被害者支援要員に対して、犯罪被害者支援において必要となる知識等についての研修、教育等を実施している。
平成29年末現在、指定被害者支援要員として全国で3万6,708人が配置されている。
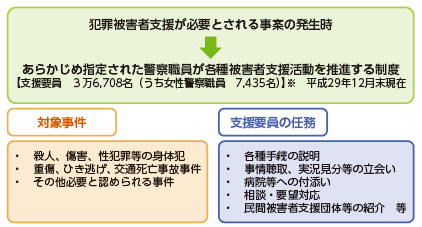
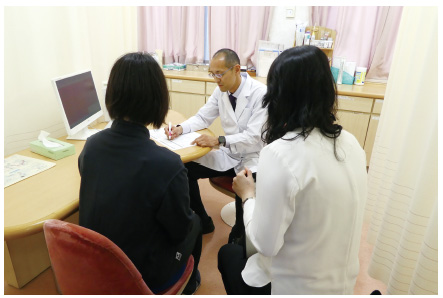
○ 海上保安庁においては、犯罪被害者等の支援及び関係機関との連絡調整を行う犯罪被害者等支援主任者を部署ごとに指定し、犯罪被害者等の具体的な事情を把握し、その事情に応じ犯罪被害発生直後から犯罪被害者等へ必要な助言、情報提供等を行うとともに、具体的な支援の説明を行うなど、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減に努めている。
(18) 交通事故相談活動の推進
【施策番号172】
国土交通省においては、交通事故相談活動に携わる地方公共団体の交通事故相談員に対して、各種研修や実務必携の発刊等を通じ、その能力の向上や、交通事故被害者等から刑事手続等の相談を受けた場合の対応についての周知を図っている。
(19) 公共交通事故被害者への支援
【施策番号173】
国土交通省においては、平成24年4月、公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、公共交通事故被害者支援室を設置し、被害者等から事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な関係機関の紹介等を行っている。
30年度においては、公共交通事故発生時には、被害者等からの相談を聞き取って適切な相談窓口を紹介し、平時には、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事業者における被害者等支援計画の策定の働き掛け等を行った。
28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故に関しては、継続的に遺族会との意見交換会を開催するなどの対応を実施した。
(20) 婦人相談所等職員に対する研修の促進
【施策番号174】
厚生労働省においては、平成23年度から、国立保健医療科学院で行っている婦人相談所等指導者研修等において、配偶者からの暴力の被害を受けた女性の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるための婦人相談所等の職員に対する専門研修を実施している(【施策番号108】参照)。
(21) ストーカー事案への対策の推進
【施策番号175】
内閣府においては、地方公共団体におけるストーカー被害者支援の充実を図るため、平成29年度に「ストーカー被害者支援マニュアル」を作成し、地方公共団体及び被害者支援を行っている関係機関等に配布している。
(【施策番号165】参照)
(22) ストーカー事案への適切な対応
【施策番号176】
平成30年中の警察におけるストーカー事案の相談等件数は2万1,556件であった(警察庁ウェブサイト「平成30年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」:https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/H30taioujoukyou_shousai.pdf)。
ストーカー事案は、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、また、加害者が、被害者に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きい。
このため、警察においては、ストーカー事案をはじめとする人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案に一元的に対処するための体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に対処することとしている。具体的には、ストーカー規制法その他の法令の積極的な適用による加害者の検挙のほか、被害者等の安全な場所への避難や身辺の警戒、110番緊急通報登録システムへの登録、ビデオカメラや緊急通報装置等の資機材の活用、被害者等の保護措置等、組織による迅速・的確な対応を推進している。また、被害者等からの相談に適切に対応できるよう、被害者の意思決定支援手続等を導入している。
さらに、逮捕状請求における被疑事実の要旨記載に際しての被害者に関する事項の表記方法への配慮、仮釈放又は保護観察付執行猶予となった者に関する保護観察所等との連携強化、被害者支援における婦人相談所、法テラス等の関係機関との協力等、被害の拡大及び再被害の防止対策を推進している。
また、29年4月にストーカー総合対策関係省庁会議において改訂された「ストーカー総合対策」に基づき、関係機関と連携した取組を一層推進している。
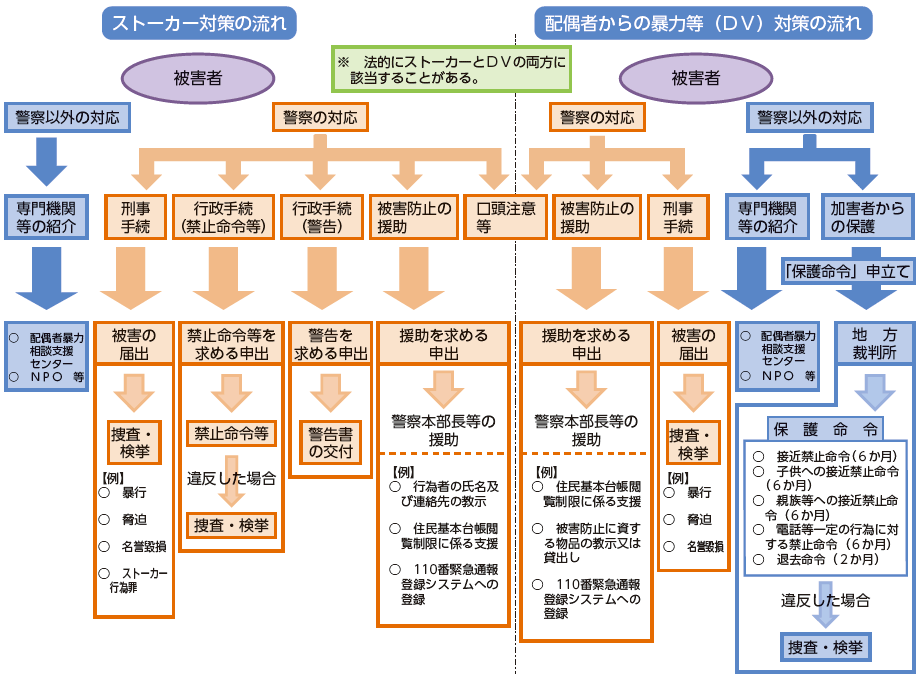
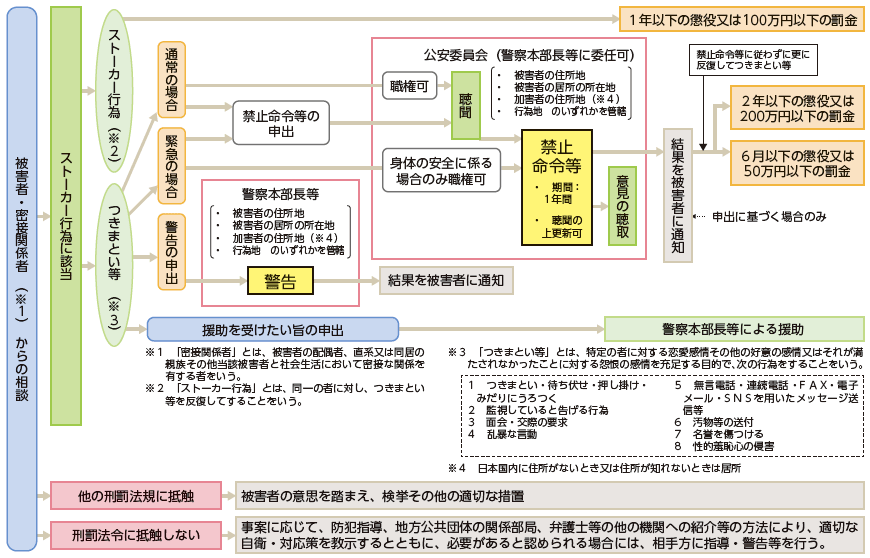
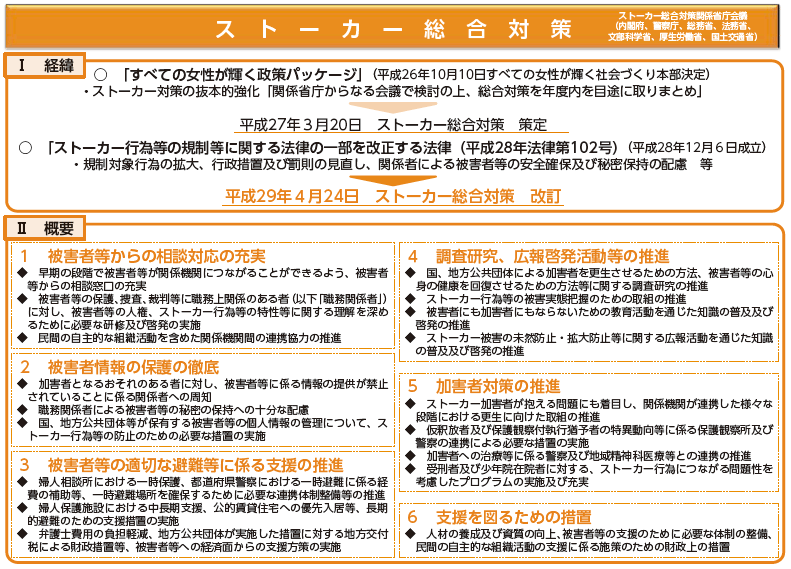
(23) 人身取引被害者の保護の推進
【施策番号177】
人身取引は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められている。これは、人身取引が、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に困難だからである。
政府では、平成16年4月から「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を開催するなどして関係行政機関が緊密な連携を図りつつ、「人身取引対策行動計画」(同年12月犯罪対策閣僚会議決定)、「人身取引対策行動計画2009」(21年12月犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な保護を推進してきたところ、引き続き人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため、26年12月、犯罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動計画2014」を決定するとともに、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催することとした。
30年5月、人身取引対策推進会議の第4回会合を開催し、我が国における人身取引による被害の状況や、関係省庁による人身取引対策の取組状況等をまとめた年次報告「人身取引対策に関する取組について」を決定・公表するとともに、引き続き、人身取引の根絶を目指し、同計画に基づく取組を着実に進めていくことを確認した。
また、同年6月の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせてバナー広告により、同年7月30日の「人身取引反対世界デー」及び同年11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせてSNSにより、それぞれ我が国における人身取引の実態、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護に係る取組に関する広報を実施し、被害に遭っていると思われる者を把握した際の通報を呼び掛けた。

(24) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実
【施策番号178】
法務省においては、犯罪被害者等に配慮した捜査や公判活動を行うため、検察官等の研修において、福祉・心理関係の専門機関の関係者を講師に招くなど、その連携・協力の充実・強化を図っている。
(25) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
【施策番号179】
地方検察庁においては、犯罪被害者等に対し、よりきめ細かな配慮を行うため、犯罪被害者等の支援に携わる被害者支援員を配置している。
被害者支援員は、犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧や証拠品の返還等の各種手続の手助け等をするほか、犯罪被害者等の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っている。
被害者支援員を対象とする研修において、被害者支援に携わる者を講師として招いているほか、日々の活動として、被害者支援団体等との意見交換の場を設けるなど、被害者支援の状況についての情報交換を行い、その連携・協力の充実・強化を図っている。また、被害者支援員の意義や役割について記載されている犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を犯罪被害者支援を行っている関係機関・団体等に配布するなどして、被害者支援員制度に係る情報提供の充実を図っている。
犯罪被害者等による電話やファックスでの被害相談の受付のため、地方検察庁等に、被害者相談専用電話番号(ホットライン)を設け、被害者支援員等が電話対応をしている。
(26) 更生保護官署における関係機関等との連携・協力、被害者担当保護司との協働による支援の充実
【施策番号180】
法務省においては、全国の保護観察所に被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司を配置し、その協働態勢の下、主として、被害に係る刑事裁判が終了した後又は被害に係る加害者が保護処分を受けた後に、犯罪被害者等に対して相談・支援を行っている。相談・支援の実施においては、犯罪被害者等の悩みや不安を傾聴するとともに、必要な情報を提供するなどしている。また、支援の円滑な実施及び支援内容の充実を期するため、国や地方公共団体の機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等との連携の強化を図るとともに、更生保護における犯罪被害者等施策の周知に努めている。
(27) 被害者担当の保護観察官及び保護司に対する研修等の充実
【施策番号181】
法務省においては、刑事裁判及び少年審判終了後の相談対応の充実のため、保護観察所に配置されている被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司を対象とする研修において、犯罪被害者等やその支援に携わる実務家による講義、事例研究及び犯罪被害者支援の実践的技能を修得させるための演習等を実施し、犯罪被害者等の置かれている現状や心情等への理解を深めるとともに、適切な対応を確実にするように努めている。
(28) 犯罪被害者の相談窓口の周知と研修体制の充実
【施策番号182】
法務省の人権擁護機関においては、調査救済制度周知用リーフレットを作成・配布し、法務省の人権擁護機関が実施する人権相談や調査救済制度の周知に努めている。
また、「子どもの人権110番」、「子どもの人権SOSミニレター」(料金受取人払の封筒兼便箋)、「女性の人権ホットライン」、「インターネット人権相談受付窓口」等の各種相談窓口についても、法務省のウェブサイトや広報資料に掲載するなど、積極的な広報に努め、その周知を図っている。
さらに、人権相談や調査救済事務に従事する職員を対象に、研修を実施し、犯罪被害者等に係るものを含む人権侵害の被害の救済に的確に対応するための体制強化を図っている。
人権擁護委員に対しては、犯罪被害者等に係るものを含む人権問題全般に適切に対応できるよう、適切かつ十分な研修の実施に努めている。

(29) 犯罪被害者である子供の支援
【施策番号183】
法務省の人権擁護機関においては、いじめ・体罰・虐待といった子供の人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、児童相談所等の関係機関と連携の上、事案に応じた適切な措置を講じている。
(30) 高齢者に関する人権相談への対応の充実
【施策番号184】
法務省の人権擁護機関においては、法務局に出向くことが困難な高齢者施設等の社会福祉施設の入所者やその家族が施設内で相談できるよう、施設の協力を得て、臨時に特設の人権相談所を開設して、入所者等からの人権相談に応じている。また、介護サービス施設・事業所に所属する訪問介護員等、高齢者と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなどの連携を図っている。
(31) 法テラスによる支援の検討
【施策番号185】
ア 認知機能が十分でないために弁護士等の法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない高齢者・障害者等を対象とした資力にかかわらない法律相談援助制度の創設や、民事裁判等手続の準備及び追行に限定されていた代理援助・書類作成援助の対象行為を、認知機能が十分でない高齢者・障害者等に対しては、生活保護給付に係る処分に対する審査請求等、一定の行政不服申立手続の準備及び追行に拡大することを内容とする総合法律支援法の一部を改正する法律が平成28年5月に成立し、30年1月から施行された。
【施策番号186】
イ ストーカー、配偶者からの暴力等及び児童虐待の被害者を対象とした資力にかかわらない法律相談援助制度の創設を内容とする総合法律支援法の一部を改正する法律が28年5月に成立し、30年1月から施行された。
(32) 地域包括支援センターによる支援
【施策番号187】
地域包括支援センターにおいては、地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援のみでは十分に問題を解決することができない、又は適切なサービス等につながる方法が見付けられないなどの困難な状況にある高齢者に対し、市町村、保健所、医療機関等と連携を図りつつ、成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応等に取り組み、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行っている。
(33) 地方公共団体に対する子供・若者育成支援についての計画に関する周知
【施策番号188】
内閣府においては、都道府県・政令指定都市に対し、平成31年2月に開催した都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議において、子ども・若者育成支援推進法に基づく子供・若者育成支援についての計画を作成又は変更する場合には、「子供・若者育成支援推進大綱」(28年2月子ども・若者育成支援推進本部決定)に盛り込まれた「犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応」に関する記述も勘案するよう、周知した。
(34) 学校内における連携及び相談体制の充実
【施策番号189】
ア 【施策番号55】参照
【施策番号190】
イ 文部科学省においては、学校において虐待を受けた子供の早期発見、早期対応が可能となるよう、虐待を受けた子供への対応、健康相談の進め方等についてまとめた参考資料も活用しながら、養護教諭等の資質向上のための研修等の内容の充実を図っている。
(35) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実
【施策番号191】
児童生徒による暴力行為の発生件数が依然として相当数に上っており、また、教職員の体罰や児童生徒間のいじめにより重大な被害が生じる事案も引き続き発生していること等が教育上の大きな課題となっている。これらを踏まえ、文部科学省においては、学校における教育相談体制の充実に取り組むとともに、都道府県・政令指定都市の教育委員会や学校に対して、
- 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる暴力行為やいじめ事案については、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点等から、早期に警察へ相談・通報し、警察と連携した対応を講じることが重要であること。
- 教員が体罰を目撃した場合や学校が体罰や体罰を疑われる事案の報告・相談を受けた場合には、事実関係の正確な把握に努めるとともに教育委員会へ報告すること。
- 学校が体罰の訴えや教員等との関係の悩みを相談することができる体制を整備し、相談窓口の周知を図ること。
等を示し、教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力や相談を受け付ける体制の整備を促している。
(36) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進
【施策番号192】
不登校児童生徒への支援について初めて体系的に定めた、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が、平成28年12月に成立し、29年2月から全面施行された。
文部科学省においては、同法を踏まえ、同年3月に、学校が不登校児童生徒に対し組織的かつ継続的支援を推進するなどの不登校児童生徒への支援に関する施策を推進するための基本的な指針を策定し、同法及び同指針の趣旨等を教育関係者に周知した。
また、不登校児童生徒への支援に際して中核的な機能を果たす教育支援センター等の設置促進、機能強化等に関する実践研究等を実施している(トピックス「不登校児童生徒に対する支援について」参照)
(37) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実
【施策番号193】
ア 厚生労働省においては、医療機関等が犯罪被害者等の支援を行っている関係機関・団体等と連携・協力できるよう、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供を必要に応じて実施するなど、適切に対応している。
【施策番号194】
イ 保健所や精神保健福祉センターにおいては、医療機関等の関係機関と連携しつつ、犯罪被害者等に対して、精神保健に関する相談支援を実施している。
精神保健福祉センターにおいては、専門知識を有する者による面接相談や電話相談(「こころの電話」)の窓口を設置し、地域住民が気軽に相談できる体制を整備している。また、必要に応じ医師による診察を行い、医療機関への紹介や医学的指導等を行っている。
(38) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導及び好事例の勧奨
【施策番号195】
警察庁においては、情報提供をはじめとする基本的な犯罪被害者支援施策が確実に実施されるよう、各種会議等を通じて都道府県警察に対し指導するとともに、好事例を紹介することにより同様の取組を勧奨している。また、毎年、被害者支援担当者体験記を発行し、各都道府県警察に配布している(コラム「警察職員による被害者支援手記」参照)。
(39) 「被害者の手引」の内容の充実等
【施策番号196】
ア 都道府県警察においては、刑事手続の概要、犯罪被害者等のための制度、犯罪被害者等支援に係る関係機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」を、被害者連絡の対象者に配布するとともに、刑事手続や犯罪被害者等のための制度について情報提供する場合にも広く活用している。
また、警察庁においては、犯罪被害者等のための制度に関する情報を警察庁ウェブサイト「警察による犯罪被害者支援ホームページ」(http://www.npa.go.jp/higaisya/index.html)に掲載し、紹介している。
【施策番号197】
イ 【施策番号129】参照
(40) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知
【施策番号198】
警察においては、犯罪被害遺児に対する奨学金給与事業等を実施している公益財団法人犯罪被害救援基金(http://kyuenkikin.or.jp/)について情報提供を行っている。同基金では、昭和56年5月の設立以来、平成31年3月末までに2,054人の犯罪被害遺児を奨学生として採用し、約26億104万円の奨学金を給与している。また、同基金においては、20年12月から、基本法の趣旨を踏まえ、現に著しく困窮している犯罪被害者等であって、社会連帯共助の精神にのっとり特別な救済を図る必要があると認められる者に対して支援金を支給する事業を実施しており、20年度から30年度にかけて、海外での殺傷事件の被害者等6人と、現に著しく困窮している被害者等4人に総額2,250万円を支給している(損害賠償請求制度に関する情報提供の充実については、【施策番号3】参照)。
○ 海上保安庁においては、ウェブサイト(https://www.kaiho.mlit.go.jp/questions/hanzaihigai/shien.html)で犯罪被害者等支援制度に係る周知を図るとともに、犯罪被害者等支援に係る業務を専門的かつ総合的に取り扱う警務管理官の指導の下、犯罪被害者等支援主任者に指名された海上保安官により、関係機関との連携・情報提供等が行われている。
(41) 刑事の手続等に関する情報提供の充実
【施策番号199】
ア 【施策番号128】参照
【施策番号200】
イ 【施策番号130】参照
(42) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大
【施策番号201】
都道府県警察においては、性犯罪被害者から被害相談等を受けるための性犯罪被害相談電話窓口の設置、相談室の整備等を推進し、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充を図っている。都道府県警察本部において、女性警察官等による性犯罪被害相談電話の受理体制及び相談室が整備されており、平成29年8月に、性犯罪被害者がより相談しやすくなるよう、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号(#8103(ハートさん))を導入した(トピックス「性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号」参照)。
また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、犯罪被害者支援団体が提供し得る支援の内容や秘密が守られること等を十分に説明した上で、当該被害者の同意を得てその被害者の連絡先や相談概要等を犯罪被害者等早期援助団体※に提供するなど、当該被害者が早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるように努めている。
(42) 法テラスによる支援
【施策番号202】
ア 【施策番号2】参照
【施策番号203】
イ 法テラスの犯罪被害者支援業務においては、警察庁や日本弁護士連合会等の関係機関・団体と十分な連携を図っていくことが求められている。このため、これらの関係機関・団体に法テラスについて周知するとともに、各都道府県警察等が事務局となって主催している被害者支援連絡協議会やその分科会に参加したり、犯罪被害者週間における啓発・広報活動等を協力して行ったりするなど、犯罪被害者支援に関係する機関・団体との連携・協力関係の強化を図っている。
また、弁護士会や犯罪被害者支援団体との連携・協力の下、犯罪被害者等が必要とする支援にたどり着けるよう、犯罪被害者等の状況に応じた最適の専門機関・団体を紹介するコーディネーターとしての役割を果たせるように努めている。
法テラスが運用している犯罪被害者支援ダイヤルにおける平成30年度中の問合せ件数は1万5,145件であった。主な問合せ内容は、生命・身体犯被害、配偶者からの暴力等、性被害、ストーカー被害等であった。
同年度中の全国の地方事務所における電話及び担当者との面談による犯罪被害者支援に関する対応件数は1万4,035件であった。
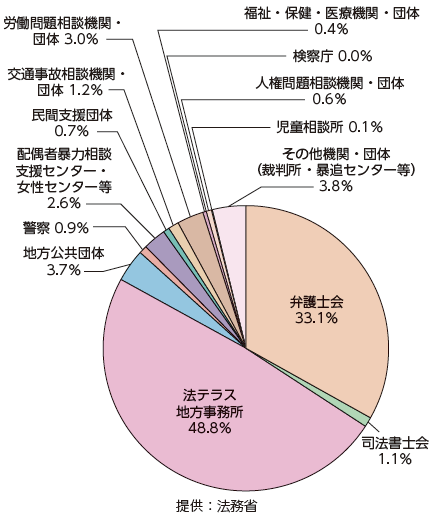
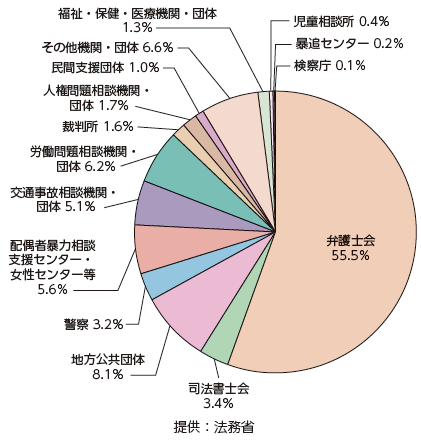
| 年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犯罪被害者支援ダイヤル 問合せ件数 |
10,482 | 9,780 | 11,048 | 11,321 | 13,137 | 13,056 | 12,014 | 13,461 | 15,145 |
| 地方事務所 対応件数 |
14,089 | 13,096 | 15,582 | 14,081 | 12,695 | 13,380 | 13,825 | 12,717 | 14,035 |
| 提供:法務省 | |||||||||
【施策番号204】
ウ 法テラスにおいては、被害を受けた時からの時間的経過の長短を問わず、情報提供等を通じた支援を行っている。
【施策番号205】
エ 【施策番号127】参照
(44) 自助グループの紹介等
【施策番号206】
警察においては、犯罪被害者等の要望を踏まえつつ、相談や支援等の機会を通じて、又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体を介して、犯罪被害者等に自助グループを紹介している。
(45) 犯罪被害者等施策のウェブサイトの充実
【施策番号207】
警察庁においては、犯罪被害者等施策に関する各種情報(関係法令、相談機関、地方公共団体における総合的対応窓口等)や犯罪被害者白書概要版の英文をウェブサイト(警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」:https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html)に掲載しており、その内容の充実を図っている。
また、SNS(警察庁フェイスブック「犯罪被害者等施策」:https://www.facebook.com/npa.hanzaihigai/)を活用し、各地におけるイベントの紹介等、犯罪被害者等施策に関する情報の発信を行っている。
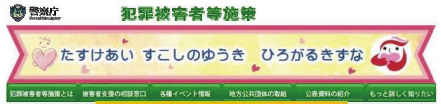
(46) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等
【施策番号208】
在外公館においては、現地警察への犯罪被害の届出に関する助言や弁護士・通訳者のリスト、医療機関に関する情報提供のほか、本人が連絡できない場合の家族との連絡の支援や緊急移送に関する助言、遺体の身元確認に関する支援等を行っている。
外務省においては、海外での邦人の犯罪被害を未然に防止し、被害に遭った場合の対処法について広く周知を図るため、広報冊子「~海外旅行のトラブル回避マニュアル~海外安全虎の巻」を毎年改訂の上、全国の都道府県旅券事務所や旅行会社、団体等に配布するとともに、「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf)及び海外安全アプリにも掲載するなど、海外における邦人の犯罪被害に関する情報を分かりやすく伝えるとともに、国民が事前にこれらの情報を得る機会が増加するよう取り組んでいる。
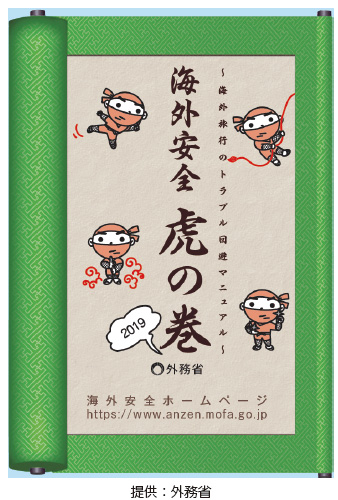
平成29年に、在外公館及び公益財団法人日本台湾交流協会が取り扱った海外における犯罪被害に係る援護件数は4,531件(4,710人)であり、このうち最も多いものは「窃盗被害」(3,676件、3,813人)となっており、これに「詐欺被害」(320件、332人)、「強盗被害」(270件、287人)が続いている。
| 件名 | 件数 | 人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 9 | 12 | ||||
| 傷害・暴行 | 82 | 91 | ||||
| 強姦・強制猥褻 | 24 | 22 | ||||
| 脅迫・恐喝 | 48 | 52 | ||||
| 強盗・強奪 | 270 | 287 | ||||
| 窃盗 | 3,676 | 3,813 | ||||
| 詐欺 | 320 | 332 | ||||
| 誘拐 | 0 | 0 | ||||
| テロ | 0 | 0 | ||||
| その他 | 102 | 101 | ||||
| 計 | 4,531 | 4,710 | ||||
| (注) 在外公館が援護を実施した事案のみであり、発生した全ての事案ではない。 | ||||||
| 提供:外務省 | ||||||
警察庁においては、外務省と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報の収集を行っている。
都道府県警察においては、関係機関・団体と連携し、帰国する犯罪被害者や日本国内の遺族等に対して、国外犯罪被害弔慰金等支給制度の裁定申請に係る教示や国内での支援に関する各種情報の提供、帰国時の空港等における出迎え等の支援活動に努めている。
(47) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進
【施策番号209】
警察庁においては、平成29年度犯罪被害者週間の徳島大会におけるテーマに性暴力被害者支援を取り上げ、被害が潜在化しやすい性暴力被害者が置かれている状況や支援の必要性等について、広く国民に周知し、その理解促進を図り、社会全体で支える気運の醸成に努めた(犯罪被害者週間については、トピックス「犯罪被害者週間」を、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大については、【施策番号201】及びトピックス「性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号」を、その他相談体制の充実等に関する取組については、【施策番号168】を、それぞれ参照)。
法務省の人権擁護機関においては、法務局・地方法務局に専用相談電話「子どもの人権110番」を設置し、人権侵害を受けた子供が安心して相談できる環境を整備して、人権擁護委員や法務局職員が相談に応じている。
また、30年8月29日から9月4日にかけて、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間とし、相談時間を延長するなどして子供の人権問題に関する相談体制の充実に努めた。
さらに、教師や保護者等身近な者に相談できない子供の悩みごとを的確に把握し、学校や関係機関と共に連携を図りながら様々な人権問題に対応できるよう、同年5月下旬から7月上旬(一部地域においては10月中旬及び11月中旬)にかけて、全国の小・中学校の児童生徒全員に、「子どもの人権SOSミニレター」を配布するとともに、法務省のウェブサイト上に「インターネット人権相談受付窓口」を開設し、インターネットを通じてパソコン、携帯電話及びスマートフォンからの相談をいつでも受け付ける体制を整備するなど、相談体制の強化を図っている。
法務局・地方法務局やその支局の人権相談窓口のほか、社会福祉施設等の特設相談所において、犯罪被害者等からの人権相談に応じている。また、犯罪被害者等である女性からの人権相談については、「女性の人権ホットライン」を設置するとともに、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を30年度は11月12日から同月18日にかけて実施し、相談体制の充実に努めている。さらに、外国人からの人権相談について、全国50か所全ての法務局・地方法務局に「外国人のための人権相談所」(英語・中国語・韓国語・フィリピン語・ポルトガル語・ベトナム語の6か国語に対応)を設置するとともに、「外国語人権相談ダイヤル」(前記6か国語に対応)及び「外国語インターネット人権相談受付窓口」(英語・中国語に対応)を開設し、犯罪被害者等が外国人である場合にも対応できる体制をとっている。
なお、30年中における犯罪被害者等からの相談件数は137件であった。
また、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため、「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種啓発活動を実施している。
法テラスにおいては、犯罪被害者支援ダイヤルにより、匿名での相談にも対応できる体制を整備しているほか、弁護士会等との連携の下、各都道府県において、犯罪被害者支援の経験や理解のある複数の女性の弁護士を確保している。31年3月末現在、女性の弁護士数は848人である。
(文部科学省における取組は、【施策番号55】参照)

