1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
トピックス 地方自治体における犯罪被害者等支援~長崎県犯罪被害者等支援条例の制定について
1 条例制定までの経緯
・ 条例制定の契機
長崎県では、令和元年7月16日、「長崎県犯罪被害者等支援条例」を公布・施行したが、県が条例制定に向け本格的に動き出すきっかけとなったのは、条例制定を求める県民の声が、請願、意見書等の形となって高まりをみせたことである。
・ 課題整理
県では、まず県全体の犯罪被害者等支援(以下このトピックスにおいて「支援」という。)の充実に向けた課題整理を行った。
その上で、県全体の支援の更なる充実のためには、市町との連携・協力が不可欠であることから、市町との協議の場を設けて、課題解決のため、条例制定を視野に入れた検討を進めることとした。
・ 市町との協議
協議の結果、市町は、県と市町が一体となった支援の充実の重要性と条例制定の必要性を認識していること、さらに一部の市町では、県全体で支援の足並みを揃えるため、条例制定について県のイニシアチブを求めていることを確認することができた。
なお、この市町との協議会は平成30年度に3回実施したが、最終的に県条例の中に「市町の責務等」の規定を設けることについての合意形成にも大きな役割を果たした。
・ 有識者会議の開催
市町との協議と並行して、教育、被害者支援団体等県の支援に関係する有識者6名からなる「長崎県犯罪被害者等支援懇話会」を設置し、県の支援充実に向けた課題と、条例制定の必要性について意見を伺うこととした。
平成30年度に4回の懇話会を開催した結果、支援の課題解決に必要な施策及び取組を推進するためには、条例制定が必要との中間意見を頂くとともに、条例素案についても検討を行った。
・ 条例の公布・施行
市町との協議、有識者の意見聴取、パブリックコメントの実施を経て、条例の公布・施行に至った。
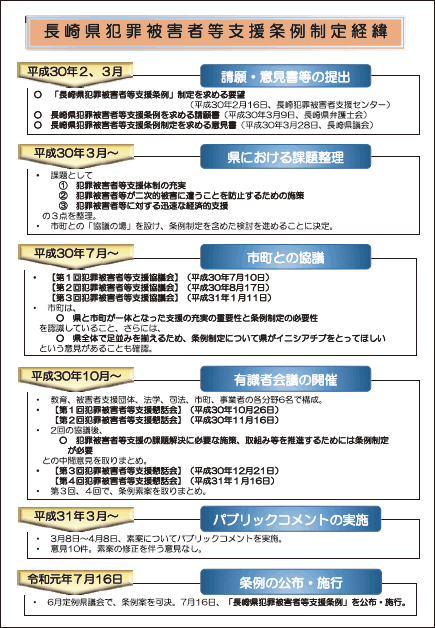
2 条例制定後の取組
・ 犯罪被害者等支援計画の策定
令和元年12月、条例を根拠とした新たな支援計画である「長崎県犯罪被害者等支援計画」を策定した。
・ 推進体制の整備
庁内の推進体制として「長崎県犯罪被害者等支援推進会議」を、また、県と市町の推進体制として「長崎県市町犯罪被害者等支援推進協議会」をそれぞれ新設した。
なお、民間団体を含めた推進体制は、県警察本部長を会長とする既存の「長崎県被害者支援連絡協議会」を活用することとし、これら3つの推進体制が県の総合的対応窓口を中心に相互に連携・協力することにより、県全体の犯罪被害者等支援を推進する体制を整備した。
・ 緊急支援体制の整備
死傷者多数等重大な事案が発生した際の支援の実施に関して、「長崎県被害者支援連絡協議会」を核に、前記推進体制が連携して対応する仕組みを県警察が中心となって整備した。
・ 庁内・市町との連携
条例制定後、支援計画の策定や推進体制の整備に当たっては、県警察を含めた庁内関係所属及び市町との協議の場をそれぞれ設けた上で合意形成を図るなど、庁内・市町との連携を重視しながら取組を進めた。特に、前述の推進体制の整備後は速やかに会議を開催し、支援計画案の内容確認、意見聴取を行ったほか、県及び市町による会議では、それぞれの取組について情報共有を図った。
・ 二次被害の防止に資する広報啓発・研修
支援についての県民の理解の増進と条例制定の周知を図るため、支援に関するシンポジウムを開催するとともに、長崎市中心部のアーケード街において犯罪被害者に関するパネル展を開催した。また、市町を含めた支援担当職員の資質向上を目的として、警察庁との共催により、行政職員を対象とした犯罪被害者等支援研修会を開催した。
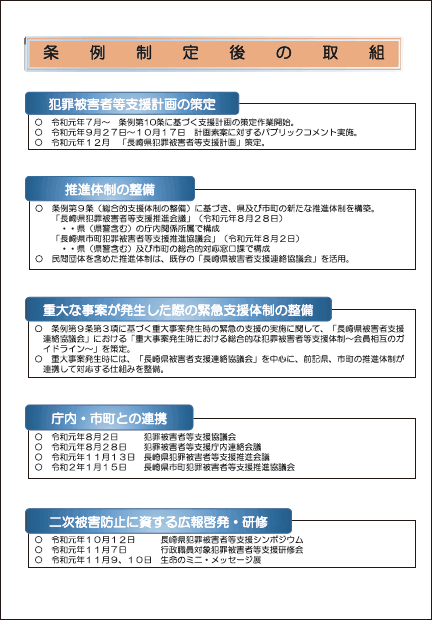
3 今後の取組について
条例制定後、県では、市町及び県警察と連携しながら、推進体制の整備、二次被害の防止に資する広報啓発等様々な取組を行ってきたが、その過程で、半数を超える市町が本年度中の条例施行を目指すなど、県全体の支援の更なる充実に向けた機運が着実に高まっている。
今後も、この機運を絶やすことなく、市町を含めた総合的支援体制の充実、県民の理解の増進等条例に掲げた目的、理念に沿った取組を継続していく。

