住民に身近な市町村域において、保健、医療、福祉、教育、警察、司法等の関係機関、団体等が、域内の虐待を受けた子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるとの観点から、平成12年度から要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止ネットワーク)の設置を進めている。
同協議会は、市町村の児童福祉主管課や児童相談所等の関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者等により構成されており、平成16年の児童福祉法の改正において、法定化され、同協議会を構成する関係機関等に守秘義務が課せられた。
これにより民間団体を始め、守秘義務が課せられていなかった関係機関等の積極的な参加と、積極的な情報交換や連携が行われており、平成17年6月1日現在、全国2,399市町村の51%に当たる1,224市町村が協議会又はネットワークを設置しており、前年度に比べ11.2%の増加が見られた。
(6) 児童相談所及び婦人相談所における一時保護児童相談所は、児童福祉法第33条第1項の規定により、必要があると認めるときは、子どもの一時保護(委託を含む。)を行っている。平成16年度の一時保護件数は1万8,885件、一時保護委託件数は6,148件となっている(厚生労働省「福祉行政報告例」より)。
また、従来から保護を要する女性について、婦人相談所による一時保護を実施しており、配偶者からの暴力や人身取引被害者等を含めた一時保護件数は、平成16年度で1万2,059件(要保護女性6,541件、同伴家族5,518件)となっている。
▼要保護児童対策地域協議会の設置
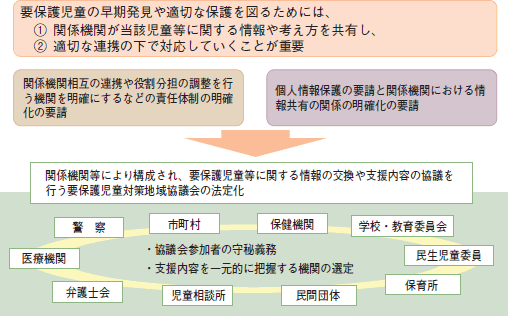
出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ
(第4回「支援のための連携に関する検討会」厚生労働省資料)
(7) 被害者等の安全確保
海上保安庁において、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあるときは、被疑者等に当該被害者の氏名又はこれらを推知されるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ被害者等の保護のための措置を講じている。