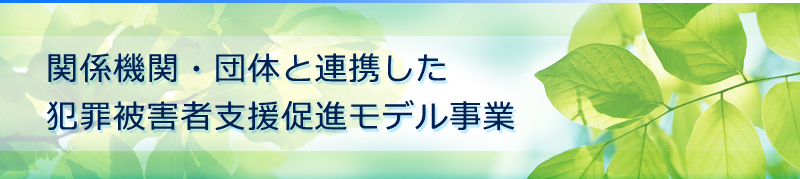
講演:「犯罪被害者にやさしい社会へ~地下鉄サリン事件の遺族体験から~」
 |
高橋 シズヱ (地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人) |
皆さん、こんにちは。地下鉄サリン事件というと、13年半前に起きた事件です。どういう事件だったのか、レジュメにだいたいまとめさせていただいています。その上に自己紹介ということで私のことをちょっと書かせていただきました。このことを織り交ぜながら話しますので、時々確認しながら話を聞いていただければと思います。
■事件直後
私が事件を知ったのは妹からの電話でした。テレビを見ていた妹が私の勤め先に電話をしてきて、事件が起こったことを知らされ、上司に付き添われて病院に駆けつけました。私は銀行でパートの仕事をしていました。主人は霞ヶ関駅で勤めていました。北海道は広いですから、鉄道より車のほうが多いと思いますけど、東京は蜘蛛の巣のように地下鉄が縦横に走っています。その鉄道業の仕事で命を落とすとは思っていませんでしたので、ほんとにびっくりしました。それに、サリンが撒かれるなんて誰も想像してなかったと思います。
病院に着くと、そこが廊下か診察室かわからないほど混乱していました。ですから、勤め先の上司が一緒に行ってくれなければ、主人の病室に行くことができなかったと思います。病室にはもう先生や看護婦さんがいなくて、冷たくなった主人がベッドに寝かされていました。長男は主人の勧めで同じ地下鉄に勤めていますが、私より先に病室に来ていました。長男は心臓マッサージとか、電気ショックとかしているのを一人で見ていたのだと思います。もう手の打ちようがないというその場にいて、一人でそれに耐えて、すごく辛かっただろうと思っています。私が冷たくなった主人にすがって泣いていたら、長男が「お母さん、もう泣くの、やめなよ。僕だって我慢してるんだから」と言っていたのを覚えています。
私は主人の顔、手、足などを全部触りましたが、その後被害者の会ができて、他の遺族に聞きましたら、触らないでくださいと、警察とかお医者さんに言われたと。なぜかというとサリンがついているから。実際に、先生とか看護婦さんが、救急搬送に当たった消防署の人なども二次被害に遭ったりしています。遺族も大事な家族の最後の身体に触れなかった人もいるという、そういう事件でした。
■司法解剖
遺族のほとんどがそうだと思いますけれども、大事な家族が殺されたという、すごくショッキングな出来事の後にもそういう大きな打撃を受けて、納得がいかない出来事が続いていきます。私の場合には司法解剖でした。事件当日に警察で「明日司法解剖を行いますから、10時に東大の法医学教室に来てください」と言われました。東大は知っていたんですが、医学部がどこにあるかは知らないですし、解剖が行われている間どこで待てばいいのか、どうやって主人を引き取ればいいのか、そういうことを警察から何も説明を受けていなかったのです。朝の10時に行って、事務員の人に言われて指示された部屋で6時間ぐらいずっと待っていました。あまりにも長く待たされていたので、どうしたのだろうと解剖室のほうに下りて行ったときに、警察官に会って、「あ、もう葬儀社の人に引き渡しましたよ」と言われたのです。ほんとに何のために待っていたのかと思いました。
私ずっと裁判を傍聴していますが、まだ松本智津夫の地裁での裁判が続いているときでした。事件が起きると犠牲者が身につけていたものは警察に押収品として持って行かれ、押収品目録が手渡されます。押収品は何年かしてから警察の人が持ってきて、裁判では使わなくなりましたのでお返ししますと言って、押収品目録と照合して返してもらうんですね。身につけていたものはそうですけど、じゃあ、解剖で摘出された主人の臓器はどうなの?と、私は思いました。
裁判が終わって死刑が確定すれば、裁判で死因のために必要な臓器は当然返してもらえるものだと思っていました。お骨のように形はならないけど、荼毘に付すんだったら、その場にいて供養をしたいと思いまして、東京地検の検事さんに「主人の臓器はどうなっていますか」と聞いたんです。そしたら検事さんが東大の法医学教室に見に行ってくれました。そしたら、冷凍とホルマリン漬けになって確かにあります、と言われました。だけど、だれがその臓器に責任を持っているかというと、裁判所でもない、検事でもない、大学の教授に権限があるわけでもない、ということがわかりました。法律が何もないです。ですから、そういうところに遺族の意向を反映してほしいと思います。返してほしいとか、医学生の役に立ててくださいとか。とりあえず実態を調べましょうということで、いま東大の教授と研究員の方がアンケート調査をなさっています。警察の遺族対応が早く改善されるといいと思っています。
■葬儀
解剖の次はお通夜、告別式です。よくテレビでお葬式の場面とかニュースでありますよね。キャスターの人とかが「気丈にも」という言葉を使う。私も言われました。でも私自身は、気丈に振る舞おうとか、しっかりしなければとか、そんな意識は毛頭なかったですね。ただただ、お葬式という世間のしきたり、流れに従っているだけでした。例えば、母に「美容院に行って来なさい」と言われて、美容院に行って告別式に出たりしました。自分の意識ではなくて、言われるままに動いていたというような気がします。 オウム事件は、起訴されただけでも17件あるんですね。そのなかで、車にサリンをかけられた弁護士さんは、実は何年か前に5歳の息子さんを交通事故で亡くされてるんです。加害者に棺の中に納めた息子さんの冷たくなった身体を触らせたと言っていました。この前も大阪でひどい事件がありましたけども、命の大切さをわかってないんじゃないかって時々思うことがあります。オウム真理教のサリンを製造した土谷正実被告人がいます。被告人質問の時、実際には地下鉄車内の床に置いて尖らせたビニール傘の先で突いてサリンを露出させましたが、土谷が言っていた事は、サリンは空気より重いからそんな床に置かないで、自分だったら網棚の上に置くと証言していました。そんな証言を聞くこと自体辛かったんですけども、こういう命の大切さを知らないオウム信者が私たちと同じこの社会にいることが信じられません。実際にサリンを突いて漏出させた、その加害者が教祖の松本智津夫のところに行って報告すると、松本智津夫は「ポアされてよかったね」と言うわけです。ポアされてよかったどころじゃない、棺の中の冷たくなった主人、それからその前で目を真っ赤にして泣いている子どもたちを見せてやりたかったと思います。
とにかくそういう常識的な手順で葬儀は進められていきましたが、なんであんなにどんどん進められていっちゃうのかと思います。
■取材者
その後ですけれども、とにかく大きな事件だったということがあるし、サリンというあまり聞き慣れない、都会にはない、この世の中にあってはならない化学物質だし、それからオウム真理教という、得体の知れない団体ということで、すごく世間の関心が高かったと思うんですね。報道もずいぶんありました。95年のテレビとか新聞、ほとんどオウム一色でした。どこのチャンネルを回してもオウム信者、オウム信者、オウムの事件ばっかり。
そんな中で、私にも取材が来ましたけれども、そういうところに出るのはすごく不快でした。そればかりじゃなくて、事後手続というか、死亡退職ですからそういう手続もしなきゃいけない、労災保険の手続もしなきゃいけないとか、追悼式とか、弔問客も多かったですから、寝ることも食べることも普通通りの生活ではなくなっていきました。取材に来ると「よろしくお願いします」と挨拶されるんですね。「本当に大変なことでしたね」と、皆さんおっしゃる。でも、あるテレビ局のディレクターは、「高橋さんには元気になってもらいたい」と、言いました。取材に来た時に「高橋さんには元気になってもらいたい」。そのあとから松本智津夫の初公判があったり、被害者が民事訴訟を起したりとか、いろんなことがどんどん起きて、私はそれからの2年間、そのディレクターの密着取材を受けました。
そのディレクターのことは、取材者で信頼できた最初のことだったし、その言葉にとても勇気づけられたので、レジュメの真ん中に書いてあると思いますが、今年の3月に出した『ここにいること』という本の中に詳しく書きました。犯罪被害者遺族というのは、事件そのものもいろいろで、亡くなった家族との違いとか、あるいは事件からどれくらいの月日が経っているかとかによっても違います。だから、取材に来る人たちもそうですけども、支援する人もどんな言葉のかけ方、遺族の心をほぐしていくかというのはすごく難しいと思うんです。私も事件後にたくさんの人に会いましたけど、このディレクターの言葉にはとても勇気づけられました。
■弁護団のサポート
事件が起った95年頃は被害者支援ということはありませんでした。個人的にはあったかもしれませんけど、きちんと法律に基づいて民間団体、あるいは警察とか、市区町村役場とか、そういう方々が組織として被害者支援をするということはなかったんです。オウム事件では、坂本事件からオウムがおかしい、オウムが危険だということをずっと言い続けてきた弁護士さんたちがいました。坂本事件というのは坂本さんが殺されたということでもあるんですけども、坂本さんがやろうとしていたことを妨害した、いわゆる弁護士業務の妨害事件ということでもあって、弁護士さんたちがずっと坂本さんたちを探していました。その弁護士さんたちが、地下鉄サリン事件の被害者のための弁護団を組んでサポートをしてくれました。
オウム事件というのはずっとオウムがおかしいと言っていたにもかかわらず、警察が捜査に入らなかった。松本サリン事件では河野さんが疑われていた。それでもオウムを捜査しなかったんです。地下鉄サリン事件が起きて初めて、河野さんが犯人じゃないとわかったぐらいですから。だから、私たちは「警察もオウムと同じぐらい責任があるでしょう」、「被害者を救済するための責任があるでしょう」とずっと言い続けてきてきました。しかし、サリン被害者の経済的な支援策とか、サリン中毒の健康被害に対しての支援策は何も講じられないままでした。
私たちは国だけに助けてくれと言っていたわけではなくて、自分たちでも損害賠償訴訟を起しました。これってすごく恐いんですよ。だって相手はオウム真理教です。提訴するというのは自分の住所と名前を相手側に出すことなのです。どんな仕返しをされるかわからない。私、お友達によく言われました。「ホームの端を歩かないでね」とか、「暗い道を歩く時は後を振り向いてね」とか、それぐらいみんな恐かったのです。でも、その恐怖を乗り越えて訴訟を起しました。5年後に勝訴しましたが、損害賠償金は1円も受け取っていません。出家信者だから財産を持っていないということもありますが、死刑になるような犯罪の加害者が、働いて賠償金をお返ししますということは当然ないですから、1円も受け取ってない。これはオウム事件に限ったことではありません。殺人事件の遺族が賠償の訴訟を起しても相手からとれないことがほとんどです。ただ、犯罪被害者等基本計画ができて、犯罪被害給付金がこの度自賠責並みに3000万、4000万、そこまで引き上げられました。
それから、オウムの破産ということがありました。私たち被害者が破産の申し立てをしてオウムは破産になりましたが、破産させることによって、つまりオウムに賠償責任をとらせることによって、オウムがこれ以上またお布施集めたりして大きくならないように、何か事件を起さないようにと、経済的にダメージを与えさせるという目的もありました。ところがオウムもアレフとか、光の輪とか名称を変えて、賠償責任を逃れようとしました。そういうこともあったし、それから破産管財人の阿部三郎先生、元日弁連の会長さんですけど82歳です。私たちのためにご尽力くださっていたのですが、これ以上は限界ですということで、今年の3月に管財業務が終わりました。そしたらやっと国が動いてくれたんです。オウムの被害者救済法が今年の6月にできました。
その間、私はずっと被害者救済を訴えていて、皆さんも私のことをテレビでご覧になったり、新聞で読まれたりして、また高橋が出てると思われたかもしれませんけど、私は必死でした。それは主人の無念さもありますが、サリン中毒の被害者の人たちに差別がありました。偏見もありました。「サリンってうつるんじゃないの」とか、生命保険に入れないとか。それから、地下鉄サリン事件というのはたまたまこの電車に乗っていたということで、職場とか地域では一人だったりすると、孤立してしまいます。ひどい場合は、家族の中で「あなた、いつまでそんなだらだらしているの」と言われて辛い思いをしています。頭痛とか、目を収縮する筋肉をやられてものすごく眩しかったりする。サングラスをかけたり、暗い部屋にいたりする。そういう表に出られない被害者がいるのです。そういう人たちの代わりに私は言っていこうと必死でした。
それともう一つ、私が必死だったのは、事件が起きるまで私は普通の主婦でした。特別な人間ではありません。こんな大勢の方の前で話をするなんて夢にも思っていませんでした。事件が起きたと同時に、まず接するのが警察の人です。あと検事さん。それから取材に来るメディアの人たち。それから裁判も行われる。そういう人たちは、いわゆる専門的な分野の人たち、専門家と言われるような人たちです。そういう専門分野の中に、事件に遭って遺族になった途端に投げ込まれるのです。全然わからないです、言葉とか。皆様方も福祉のことで専門分野に入っているわけですけども、遺族はそういう専門的なことがわからないのに、とくに裁判で使われる言葉なんか全然わからないです。
でも、本を買ったりして、人が話していることがわかるようにして、それから自分で判断して決断しなきゃいけない。これから訴訟を起そうとか、弁護士さんと話さなければいけないとか、あるいは加害者から手紙が来る。その加害者の手紙のことで相手側の弁護人と話す。そういうことで私は必死でした。どうやって同じように話ができるかということでは、とても必死になってやってきました。
民事訴訟を起した代理人の弁護士さんたちというのは、いわゆる金銭でしか、その被害回復の度合いというのが計れないわけですから、最初に「オウムの破産で配当が20%です」と言われたときには、弁護士さんは「いやいや、僕たちの仕事は皆さんに100%被害回復してもらって当然。ところが20%だったらまだまだ、これは20点ですよ。僕たちの仕事は20点です」と言って、弁護士さんはがんばってくれました。
あと、実はオウムの被害者救済法ができて、4千人の人たちが給付金の支給対象になっていますが、絶対にその4千人みんなに受け取っていただきたい。なんでかというと、この支払ったお金を国がオウムに取立てるのです。この金額が少なければ、オウムは足かせがなくなって、また増長するかもしれない、そういう危険があったりするので、私たちはその給付金をきちんと被害者全員が受け取ってほしいと思っています。
■刑事裁判
刑事裁判の話をします。今は希望する被害者遺族に公判予定日が検察から教えてもらえますけど、私の時には全然教えてもらえなくて、メディアの人たちに教えてもらいました。オウムの現状というのも、犯人がまだまだ捕まっていないというような状況の時にはすごく恐怖がありました。そういう時に警察に「オウムの今の状況はどうなってますか?」と聞いたら、警察は新聞のコピーを持ってきたんです。捜査情報はすべて教えられないというのはわかりますが、相手側に恐怖を持っていて、そこに乗り込んでいくわけにはいかないのです。私はメディアの人たちからいろいろオウムの情報などを聞くことができました。
それから、裁判を傍聴していて、こういうことがありました。まず法廷に入る前に廊下に並びますが、オウムの信者と一緒です。オウムの信者に限らず、法廷に入る前は被告人の家族と一緒に並ぶことがあります。これ、遺族は辛いです。今はたぶん民間の支援団体もありますから、そういう支援者の人が側に付き添って一緒にいてくれると思いますが、被告人の弁護士さんがその廊下で被告人の家族と打ち合わせをしたりする時があります。一緒に並んでいるわけですから、そういうのが全部聞こえたりします。嫌だなと思います。これからはたぶん裁判所の中にも被害者の控室ができて、加害者と一緒に並ばなくても済むようになるとは思います。東京地裁と大阪地裁にはできたと聞いています。そういうのはどんどん言っていかないと、変わっていかない。被害者、遺族が言えなくても、支援にあたる人は言ってあげてほしいなと思います。
それから、検察官の尋問で、ひどいのがありました。サリンをつくった遠藤とか土谷の法廷ですけども、被害者のお兄さんが証言した時がありました。その被害者は車いすで寝たきりという状況の人ですけど、彼女はどうしてその被害に遭ったかというと、その日、3月20日は研修が行われるので、会社ではなくて研修所に行くことになっていました。3月19日、お兄さんに「研修所にはどう行けばいいの?」と聞いたわけです。「こうやって行けばいいんだよ」と教えてあげて、3月20日はお兄さんの子どもを保育園に送りながら、妹さんも車に乗せてその最寄り駅まで送って行った。そしたら、妹さんが乗った地下鉄にサリンが撒かれて、妹さんは心肺停止状態。今は家族の介護なしには生活できないという、そういう被害に遭ってしまった。そのお兄さんが土谷被告の法廷で証言しました。検察官が、「もしあなたが妹さんを送って行って妹さんがその電車に乗らなければ被害に遭わなかったのですね」と尋問したんですね。被害者や遺族が被告人の横で証言するのはほんとに緊張しますから、お兄さんは、「はい、そうです」と答えましたが、休憩時間になって外に検事さんも出たときに、私、検事さんに言いました。「今の尋問ひどいじゃないですか。あれじゃ、いかにもお兄さんが悪いみたいじゃないですか」。検事さんは黙って聞いていましたが、その法廷が終わってお兄さんと一緒に帰ろうとしていた時、検事さんがお兄さんに謝っていました。気がついて、そうやって謝ってもらってよかったと思いますけど、ほんとにまだまだ被害者の心情とか状況がわかってもらえないことが多いと思いました。
それから、ほんとにそのお兄さんの証言の時にいろいろ起ったんですけども、裁判官が居眠りをしていた時がありました。3人裁判官が並んでいて、右陪席の裁判官がずっと下を向いているのです。全然動かないのです。おかしいね、おかしいねって、遺族が何人か、みんな証言に出るので傍聴席にいたんです。傍聴席から何か言うと、叱られて退廷させられちゃうんですね。私は退廷覚悟で、だってお兄さんが辛い話で証言している時ですから、絶対これはいけないと思って、「裁判官、居眠りしてませんか」って叫んでしまったんです。そしたら、その裁判官はパッと頭を上げて……。退廷させられませんでした。何事もなかったかのように坦々と裁判は進んでいきました。「ああ、やっぱり居眠りしていたんだ」と思いました。そんなこともありました。
あと、被告人から手紙が来ます。これ、被告弁護人の常套手段だって聞いていますが、謝罪の手紙ですね。地下鉄サリン事件の被告人は何人もいるので、何回もそういうことが起こるんですけど、最初に被告人からの手紙を受け取ってくださいって弁護人に言われた時に、どういう意味かわからなかったです。民事裁判を起していますから、民事の担当の弁護士さんに相談したのです。そしたら、刑事裁判中の被告人からの手紙というのは謝罪で、それは当然裁判に反映される、情状の対象になる、ということを初めて聞きました。ですから、それは断りました。そういうことも知らなかったですね。
■アメリカ研修旅行
それから、皆さんに是非聞いていただきたいのはアメリカの研修旅行の話です。日本の被害者支援というのは今でこそ法律ができて、いろいろなところで相談窓口ができています。地下鉄サリン事件が起きた95年というのは被害者支援の芽はありました。でも、それは育ってなかったのですね。地下鉄サリン事件が起きて5500人という被害者が出たときに、被害者というものが認知されてきました。被害者の支援というのは早ければ早いほど被害回復が早いということがわかってきていて、欧米では被害者支援が20年も30年も進んでいるということがありました。そのアメリカに支援の研修旅行に行きましょうということになりました。茨城県にある常磐大学の長井教授が連れていってくれまして、3週間ぐらい、支援組織とか、検察官事務所とか、裁判所とか、自助グループ、いろんなところに行って研修を受けてきました。
その時の資料をちょっと皆さんにお見せします。ツーソンの「Survivors of Homicide Victims」(「殺人事件の遺族」というような意味)での研修資料です。赤い波形の線がおわかりいただければいいんです。ここに「DEATH」と書いてあって、死に巡り合って、そこからいろいろな出来事が起きて、遺族にどういう感情の変化が起きるかということがずっと書かれているのです。
犯罪被害に遭ったら、時とともにだんだん右肩上がりに被害回復していくと、皆さんはたぶん思われると思うんですけど、実際にはいろんな出来事によって波形のように、戻ったり、上昇したりというように感情の変化が起きます。メディアが来て、それから警察の事情聴取があって、犯人が逮捕されて、裁判が始まって、それから経済的なものでは葬儀とかの出費があったり、被害のために仕事ができなくなって収入がなくなったり、あるいは裁判の傍聴に行くためにその交通費がかかったりとか。私は東京で東京地裁での裁判ですからそんなにかかりませんが、事件が起きた場所が、例えば北海道だったら北海道での裁判まで来なきゃいけないわけです。そういう経済的負担も大きい。そういうなかで遺族にいろいろな感情が起きてくるということです。
皆さんのお手元に資料をお配りしていますが、それはフィラデルフィアの暴力反対同盟という被害者支援組織で研修を受けた時の話です。自助グループに参加しているご両親が、「3ヶ月前に私の娘が殺されました。私たちはすぐ精神科の先生のカウンセリングを受けて、こういうことを教わりました」と言って、1枚の紙を取り出して、それをくちゃくちゃにまるめ、次にそれを静かに広げました。で、「これが今の私の心です」と言いました。つまり何もなかった紙にシワができている。これはどんなことをしてもきれいにはならない、シワがついたまんまなんです。こういうことをアメリカでは事件から3ヶ月の人が私たちに説明できる、説明するだけのカウンセリングを受けている。私の3ヶ月の時はどうだったか、アメリカに研修旅行に行ったのは事件から5年経った時ですけど、その時ですら全然知らなかった。こういうことがどんどん行われて、早い段階から支援を受けられれば、長い間苦しまなくて済むということがあります。
それから、支援団体がキャンペーンをやります。基金集めもやります。実はMADD(Mothers Against Drunk Driving)飲酒運転に反対する母親の会という大きな支援組織ですけども、そこではいろんなグッズを作っています。実は今日の私のこのスカーフ、飲酒運転に反対する母親の会ですから、この模様、カクテルを顕微鏡で見るといろんな模様に見える、その模様をスカーフにして渡してくれました。マグカップもあるんですけども、そういうものを作ってキャンペーンを行って資金集めもやったりしています。そういうふうに努力しながら、自分たちの存在もPRしているということでした。
それから、犯罪被害者の自助グループがあります。それは、例えばさっき話したような家族の中でも「あなた、何してるの、いつまでめそめそ泣いてるのよ」などと傷つけられることがあるわけですけども、同じ被害者同士、遺族同士ならば、その辛さを分かち合えるということがあります。それから、被害者や遺族は、いつまでも同じことを繰り返し話しますが、そういうことを「いつまで言ってるのよ」って言われることなく話をすることができる。涙を流しても「いつまで泣いてるの」って言われないで話ができるということがあります。支援者はそういう中に入って、被害者や遺族が泣いていて話ができなくなってしまった時に、そっと肩に手を置いて側にいてあげたりすると、また勇気を奮い起こして話をすることができたりするわけです。
■家族のこと
それから、家族の話をします。レジュメを飛ばしてますけども、私が今日一番したい話です。私には3人の子どもがいます。主人の両親も扶養していました。事件が起きた時は次男が高校卒業した春休みです。たぶん皆様方と年齢が近いと思いますけど、その春休み、事件が起きました。主人が一家の大黒柱で要でもあったわけですけど、残された母親と子どもたちが支え合って生活をしていくと思われるでしょうが、うちでは事件の話とか、父親の話というのが一切できませんでした。しませんでした。
最初は、事件からわずかな時に、テレビから歌が流れてきたんです。私が「これ、パパの大好きな歌だったね」と言ったら、長女が「やめてよ!」ものすごく怒って言ったのです。もうそれっきり事件の話とか、「パパが」なんて話せませんでした。だけど、私は代表世話人になってしまったし、次から次から取材が来て、夜になって子どもたちが帰ってきても取材の人がいるわけです。カメラが回っていたりする。部屋もいろんな書類が重なって、まるで事務所みたいな居間でした。そんなふうに、家の中は事件でいっぱいだった。そういうところで会話がなくて、子どもたちが私のことをどう思っているのかわかりませんでした。
事件から10年目ですけども、NHKの『人間ドキュメント』という番組の取材がありました。2人のディレクターが来て、私への取材と、もう1人のディレクターが子どもたちへの取材をしていました。それが2005年4月に放送されました。その放送を見て、私はほんとにボロボロ泣いてしまいました。その『人間ドキュメント』の中のほんの一部10分ぐらいをちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。
―― DVD放映 ――
ありがとうございました。今年の9月にNHKのアーカイブスに登録されて、「共に生きる」というところに「妻、シズヱさんの春」というタイトルで入っていますので、札幌の放送局に行ったら見ていただきたいと思います。
去年の3月に、このときに通訳をしてくれたカリンさんから、去年秘密の話を打ち明けられました。どういう話かというと、この事件から10年のシンポジウムが実際に行われ、その翌日3月20日に霞ヶ関の駅で献花が行われました。その献花にリーさんたちと一緒に行った帰り、日比谷公園の中で長女はリーさんに自分の気持ちを打ち明けたそうです。その前の年から長女はリーさんたちに会っているので、息子を失ったリーさんのことを自分の父親のように感じていたのだと思うんですね。私には言えないことをリーさんには打ち明けていました。なんて言ったのかはこの本の中に書いてあるんですけど、するとリーさんは長女に「ここにいることが大事なんだよ」と言ったそうです。私、この本を書き始めたとき、「高橋さんには元気になってもらいたい」というタイトルで書き始めましたが、書いていくうちに長女が言われた「ここにいることが大事」という、「ここにいること」をタイトルにつけようと思いました。
■最後に
皆さんにお伝えしたいのは、支援というのは一朝一夕にできるものではないということです。きょう何か自分がやったから、これで被害者や遺族にとって良いことをした、よかった、よかったということではないということです。被害回復のために何が必要なのかということは、被害者、遺族それぞれに違っていますけれども、そのニーズを知っていただくことと、そのニーズを満たすためにお手伝いをしていただければ、と思います。
レジュメの最後に「医者と患者」と書きました。いまのお医者さんは、患者さんの顔を見ないでパソコンの画面を見て診断を下す、ということがあるようですけれども、そんなことがないように、やっぱり心と心の触れあいで、そこに信頼関係を持たせてほしいと思います。「今日これをやります」という一つの形、目的というものではなくて、「ここにいること」、「ここにいますよ」ということを伝えてほしいと思います。そう感じられることが、犯罪被害者遺族がまた明日もがんばれるという、そういう勇気を持つことができます。
先ほどもお話にあったように、本当にいつ、どこで、だれが犯罪被害者になるかわからない時代ですから、一人でも多くの方に、犯罪被害者のご理解をいただいて、支援に携っていただければと思っています。
長い間ご静聴ありがとうございました。