第3節 刑事手続への関与拡充への取組
1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)
《基本計画において〔今後講じていく施策〕とされたもの》
(1) 医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進
(P8「医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進」参照)
(2) 冒頭陳述等の内容を記載した書面交付の周知徹底及び適正な運用
法務省において、犯罪被害者等の希望に応じ、公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容などを説明するとともに、冒頭陳述の内容を記載した書面などの交付を全国で実施している。
また、それらについて、会議や研修などの様々な機会を通じて検察官などへの周知徹底を図り、一層適正に運用されるよう努めている。
(3) 被害者参加人への旅費等の支給に関する検討
平成19年6月20日に成立した「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、「刑事訴訟法」が一部改正され、裁判所から参加を許された犯罪被害者等が、原則として公判期日に出席できるとともに、一定の要件の下で、証人の尋問や被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加制度」が創設され(平成20年12月1日施行)、法務省において、その円滑な運用に取り組んでいる。
さらに、第2次犯罪被害者等基本計画により、法務省において、犯罪被害者等が被害者参加制度を利用して裁判所に出廷する際の旅費等の負担を軽減するための制度の導入について検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされたことから、現在、必要な調査・検討を行っている。
(4) 被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件に関する検討
法務省において、平成20年2月5日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案」を国会に提出し(同年4月16日成立、同月23日公布)、これにより被害者参加人のための国選弁護制度が創設(「被害者参加制度」と同じく、同年12月1日施行)され、裁判所から参加を許された被害者参加人につき、その資力が乏しい場合であっても弁護士の援助を受けられるようになった。被害者参加人のための国選弁護制度の開始を受け、法テラスにおいて、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知するなどの業務を行っており、その円滑な運用に取り組んでいる。
さらに、第2次犯罪被害者等基本計画により、法務省において、被害者参加人のための国選弁護制度における被害者参加人の資力要件の緩和について、被害者参加人の旅費と併せて検討を行うこととされたことから、現在、必要な調査・検討を行っている。
(5) 公判記録の閲覧・謄写制度の周知及び閲覧請求への適切な対応
検察庁において、パンフレット等により、犯罪被害者等から刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、刑事事件の係属中であっても、閲覧・謄写が可能である旨の周知を図っている。また、刑事確定記録の閲覧に際して、犯罪被害者等に対し、被告人や証人等の住所を開示するかどうかについては、裁判の公正担保の必要性と一般公開によって生じるおそれのある弊害等を比較考慮して、その許否を判断すべきものであるところ、被害者保護の要請に配慮しつつ、適切な対応に努めている。
犯罪被害者等に公判記録の閲覧・謄写をさせた事例の延べ数は、平成23年1月から同年12月までの間に、1,311件であった*12。
(6) 犯罪被害者等と検察官の意思疎通の充実
法務省・検察庁において、犯罪被害者等の意見が適切に刑事裁判に反映されるよう、また、公判期日の設定に当たっても、犯罪被害者等の希望が裁判所に伝えられるよう、必要に応じ、適切な形で、検察官が犯罪被害者等と十分な意思疎通を図ることを、会議や研修などの様々な機会を通じて、検察官などへの周知徹底を図っている。
(7) 国民にわかりやすい訴訟活動
検察庁において、傍聴者などにも手続の内容が理解できるように、難解な法律用語の使用はなるべく避けたり、プレゼンテーションソフトなどを活用して視覚的な工夫を取り入れたりするなど、国民に分かりやすい訴訟活動を行うよう努めている。
(8) 上訴に関する犯罪被害者等からの意見聴取等
法務省・検察庁において、検察官が上訴の可否を検討するに当たり、犯罪被害者等の意見を適切に聴取するよう、会議や研修などの様々な機会を通じて検察官などへの周知徹底を図っている。
(9) 少年保護事件に関する意見の聴取等各種制度の周知徹底
法務省・検察庁において、検察官に対し、会議や研修などの様々な機会を通じて、少年保護事件に関する意見の聴取の制度、少年審判の傍聴、記録の閲覧・謄写の制度、家庭裁判所が犯罪被害者等に対し少年審判の結果などを通知する制度の周知を図っており、検察官が犯罪被害者等に対して適切に情報提供できるよう努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレットに掲載し、一般国民に対しても周知を図っている(P66(11)「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)。
| 申し出のあった件数 | 認められた件数 | |
| 意見聴取 | 2,409 | 2,313 |
| 記録の閲覧・謄写 | 8,017 | 7,886 |
| 審判結果等の通知 | 9,481 | 9,422 |
提供:法務省
(10) 少年審判の傍聴制度の周知徹底
平成20年の少年法改正により、一定の重大事件の犯罪被害者等が少年審判を傍聴することができる制度が導入されるとともに、犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲が拡大されるなどしたことから、上記のとおり、法務省・検察庁においてこれらの制度の周知を図っている(P66(9)「少年保護事件に関する意見の聴取等各種制度の周知徹底」参照)。
(11) 刑事の手続等に関する情報提供の充実
法務省において、平成20年12月から実施されている被害者参加制度や少年審判の傍聴制度など、被害者保護・支援のための諸制度について理解していただくために、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を作成している。パンフレットについては人身取引などの外国人犯罪被害者や視覚障害者等に対する支援体制の確立に努めるため、英語版や点字版、さらに内容を音声で録音したCD 版も作成している。
その他、犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を作成している。
パンフレットは、事情聴取をする際などに犯罪被害者等に手渡しているほか、検察庁や警察署など関係機関の窓口に備え付け、法務省ホームページ及び検察庁ホームページにも掲載して、イベントで配布するなどしている。また、視覚障害者用の点字版・CD 版については、全国の検察庁及び点字図書館等において閲覧等できるようにするなどして、周知を図っている。
さらに、DVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」は、全国の検察庁に配布し、犯罪被害者等に対する説明に利用しているほか、法務省ホームページ(YouTube 法務省チャンネル)で配信している。
今後も、パンフレットを検察庁や警察署のほか関係機関に備え付けて国民一般に配布していくほか、必要に応じて、パンフレットやホームページの内容を更新し、各種制度の周知徹底に努めていく。
- 法務省ホームページ:「犯罪被害者の方々へ」
- DVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」
警察庁において、「被害者の手引」の内容を充実させている(P81(22)「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)。
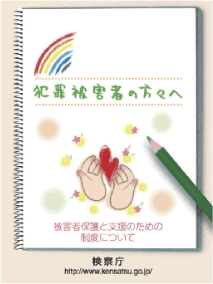

(12) 刑事の手続等に関する情報提供の充実及び司法解剖に関する遺族への適切な説明等
法務省において、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレットの内容を充実させ、配布等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の情報提供に努めている。また、犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、パンフレットについては英語版や点字版、内容を音声で録音したCD版の作成や、ホームページに掲載するなどして情報提供の充実化を図っている。
パンフレット以外にも、犯罪被害者等向けDVDを作成しており、DVDについても全国の検察庁に配布するだけでなく、法務省ホームページにおいても配信するなどし、更なる情報提供に努めている。
都道府県警察において、検視、司法解剖に関する手続などを盛り込んだパンフレットを配布し、遺族に対する適切な説明や配慮に努めている。
また、法務省においても、検察官が、捜査・公判に及ぼす支障等にも配慮しつつ、必要に応じ、適切な形で、犯罪被害者等に対し検視、司法解剖に関する情報を提供している。
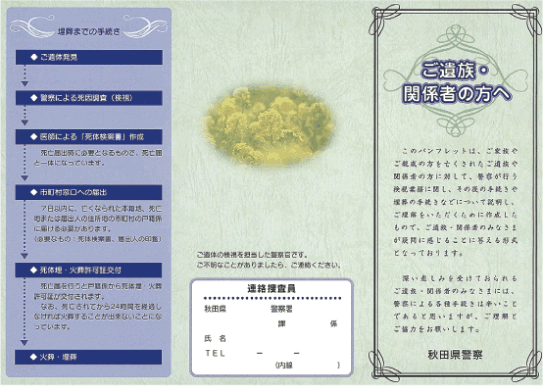
(13) 捜査に関する適切な情報提供等
警察庁において、被害者連絡実施要領や「被害者の手引」モデル案(P81(22)「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)に基づき、被害者連絡が確実に実施され、犯罪被害者等に対する適切な情報提供が行われるよう、都道府県警察に対する指導を行っている。また、被害者連絡等の支援活動を通じて得た犯罪被害者の状況やニーズのうち、民間被害者支援団体や他の行政機関と共有すべきものについては、犯罪被害者の同意を得て情報提供するなど関係機関・団体との連携を図っている。
法務省・検察庁において、捜査段階から、捜査に及ぼす支障なども総合考慮しつつ、必要に応じ、適切な形で、犯罪被害者等に捜査に関する情報を提供するよう、会議や研修などの様々な機会を通じて検察官などへの周知徹底を図っている。
(14) 交通事故捜査の体制強化等
各都道府県警察本部において、交通事故捜査担当課に設置した交通事故事件捜査統括官、交通事故鑑識官が、悪質な交通事故、事故原因の究明が困難な交通事故などについて、組織的かつ重点的な捜査、正確かつ綿密な実況見分・鑑識活動を行うとともに、交通事故捜査の基本である実況見分などについての教育を強化している。
警察庁において、交通事故捜査員に対する各種捜査研修を実施し、捜査員の能力向上を図るとともに、交通事故自動記録装置をはじめとする各種機器の整備・活用を進めるなど、科学的捜査を推進している。
(15) 不起訴事案に関する適切な情報提供
法務省・検察庁において、被害者保護の要請に配慮し、被害者等に対する不起訴事件記録の開示の弾力的運用を実施するとともに、犯罪被害者等の希望に応じ、関係者の名誉等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由について十分な説明を行うよう努めており、会議や研修などの様々な機会を通じ、検察官などへの周知徹底を図っている。
(16) 検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度の運用への協力
一定の場合に検察審査会の議決に拘束力を認める制度が平成21年5月21日に施行されたことに伴い、検察庁において、起訴議決に至った事件について、裁判所により指定された弁護士に対する協力を行うなど、その適切な運用が図られるよう努めている。
(17) 判決確定、保護処分決定後の加害者に関する情報提供拡充の検討及び施策の実施
検察庁において、事件の処理結果、公判期日、裁判結果などのほか、希望があるときは不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子などを通知する、全国統一の被害者等通知制度を実施している。なお、平成19年12月からは、同制度を拡充し、犯罪被害者等の希望に応じて、判決確定後の加害者に関する処遇状況などの情報について、検察庁、刑事施設、地方更生保護委員会、保護観察所が連携して通知を行っているほか、保護処分決定後の加害者に関する処遇状況などの情報について、少年鑑別所、少年院、地方更生保護委員会、保護観察所が連携して通知を行っている。
「判決確定後の加害者に関する情報提供」の内容として、加害者の受刑中の処遇状況に関する事項、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項などについて通知している。
また、「保護処分決定後の加害者に関する情報提供」の内容として、少年院送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年について、犯罪被害者の希望に応じて、少年院における処遇状況に関する事項、仮退院審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項を通知している。
被害者等通知制度の平成23年の実施状況については、通知希望者数は、63,542人であり、実際に通知を行った延べ数は118,933人であった。
法務省では、上記のとおり加害者に関する情報提供拡充について取り組んできたところ、第2次犯罪被害者等基本計画により、加害者の受刑中の処遇状況に関する事項、仮釈放又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項、仮釈放審理に関する事項並びに保護観察中の処遇状況等に関する事項について、また、保護観察処分及び少年院送致処分を受けた加害少年についても、少年院における処遇状況等に関する事項、仮退院審理に関する事項及び保護観察中の処遇状況等に関する事項について、適切に情報提供を行うとともに、被害者等通知制度の更なる充実について、通知制度の運用状況や加害者の改善更生、個人のプライバシーの問題などを総合的に考慮しつつ検討を行い、3年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされた。
現在、通知制度の運用状況等を考慮しつつ検討を行っている。
| 通知希望者数 | 通知者数 | |
| 平成13年 | 14,777 | 22,672 |
| 平成14年 | 47,690 | 76,691 |
| 平成15年 | 44,442 | 76,087 |
| 平成16年 | 45,967 | 75,877 |
| 平成17年 | 46,953 | 74,813 |
| 平成18年 | 50,504 | 76,377 |
| 平成19年 | 51,676 | 77,487 |
| 平成20年 | 55,330 | 91,818 |
| 平成21年 | 61,007 | 107,464 |
| 平成22年 | 62,993 | 114,996 |
| 平成23年 | 63,542 | 118,933 |
| 合計 | 544,881 | 913,215 |
※平成13~19年については、検察庁における実施状況
※通知者数とは、通知の延べ数である。
(18) 受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の発受の適切な運用
法務省において、平成18年5月、これまで原則として親族に限定されていた受刑者の面会や信書の発受の相手方について、犯罪被害者等も認めることとした指針を示し、その後、犯罪被害者等と受刑者との面会が実施されるなど、施設において適切な指導を行っている。
(19) 犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切な加害者処遇の推進等
法務省において、矯正施設に収容されている加害者に対し、被害者感情を理解させるためのオリジナルビデオ教材などを活用した「被害者の視点を取り入れた教育」指導を実施している(刑事施設において、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(平成19年6月からは「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に名称変更)の施行に伴い、平成18年5月から、必要な者に対し同教育を義務付けて実施している。)。また、同教育の充実を図るため、平成18年度以降は、犯罪被害者等や支援団体の方々から被収容者に対し直接講話するゲストスピーカー制度を拡大するとともに、平成23年度は、犯罪被害者等や犯罪被害者支援に係る関係者等を構成員として「被害者の視点を取り入れた教育」検討会を開催している。
「被害者の視点を取り入れた教育」は、被収容者に対し、自らの犯罪と向き合い、犯した罪の大きさや犯罪被害者等の心情などを認識させ、犯罪被害者等に誠意を持って対応するとともに、再び罪を犯さない決意を固めさせることを目標としており、社会復帰後の犯罪被害者等への対応、再犯の防止などにいかされることが期待できる。
また、保護処分の執行に資するため、少年に係る情報については、少年院において得られるものだけでなく、家庭裁判所や保護観察所などの関係機関や保護者から得られたものを、その都度少年簿に記載している。平成19年12月からは、犯罪被害者等についてより一層必要な情報の収集、記載ができるよう、少年鑑別所や少年院において被害に関する事項を把握した際には、少年簿に具体的に記載することとし、少年の処遇に携わる職員が確実に情報の共有を図れるようにしている。
法務省において、保護観察対象者に対する、問題性に応じた専門的処遇プログラムの内容等の充実を図るとともに、当該プログラムの受講を保護観察における特別遵守事項として設定するなどして、適切に実施している。また、保護観察対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固めさせ、犯罪被害者等の意向に配慮しながら誠実に対応することを促すため、しょく罪のための指導を適切に実施している。
保護観察所において、犯罪被害者等の申出に応じ、犯罪被害者等から被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制度において、当該対象者に対して、被害の実情を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるような指導監督を徹底している。平成23年中に、心情などを伝達した件数は112件であった。
(20) 犯罪被害者等の視点を取り入れた交通事犯被収容者に対する更生プログラムの整備等
法務省において、矯正施設に収容されている加害者に対し、被害者感情を理解させるためのオリジナルビデオ教材などを活用した指導、ゲストスピーカー制度の拡大など、「被害者の視点を取り入れた教育」の充実に努めている(P55(10)「再被害の防止に資する教育の実施等」参照)。
また、刑事施設において、必要な者には義務付けて、犯罪被害者等の視点を取り入れた交通安全指導プログラムを実施している。
(21) 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放等審理の実施
法務省において、「更生保護法」に基づき、仮釈放や少年院からの仮退院の審理に際し、犯罪被害者等からの希望に応じて、地方更生保護委員会が、犯罪被害者等から、意見などを聴き、仮釈放などを許すか否かの判断に当たって考慮するほか、許す場合には、その特別遵守事項を設定する際の参考としている。
平成23年中に、意見などを聴いた件数は273件であった。
(22) 仮釈放等審理における意見陳述に資する情報提供の拡大についての検討及び施策の実施
「更生保護法」(平成19年6月公布。平成20年6月施行。施行までの間は、その前身である犯罪者予防更生法の改正により犯罪被害者等施策を実施)に基づき、地方更生保護委員会が行う加害者の仮釈放又は仮退院の審理において、犯罪被害者等の方々から、仮釈放等に関する意見等を聴取する制度が、平成19年12月から開始され、法務省において、その円滑かつ適切な運用に取り組んでいる。
さらに、第2次犯罪被害者等基本計画により、法務省において、仮釈放・仮退院について犯罪被害者等が意見を述べる際に資するよう、被害者等通知制度における通知内容を充実させることについて、通知制度の運用状況や加害者の改善更生、個人のプライバシーの問題を考慮しつつ検討し、3年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされたことから、現在、結論を出すために必要な検討を行っている。
(23) 矯正施設職員及び更生保護官署職員に対する研修等の充実
法務省において、矯正施設職員については、矯正研修所が新規採用職員や初級幹部要員に対して実施する研修の中に、科目として「犯罪被害者の視点」を設けるなどとともに、同じく上級幹部要員を対象とする研修において、犯罪被害者団体などの関係者を講師に招くなど、犯罪被害者等の置かれている現状や心情などの理解を深める研修の充実を図っている。
更生保護官署職員については、被害者担当官及び被害者担当保護司を対象とした研修のほか、新任の保護観察官や社会復帰調整官、指導的立場にある保護観察官を対象とした研修などにおいて、犯罪被害者等施策に関する講義、犯罪被害者遺族による講話、犯罪被害者団体関係者や関係機関の職員、研究者などの専門家による被害者心理や被害者支援に関する講義などを実施している。また、それぞれの保護観察所などにおいても犯罪被害者等の心理などに関する研修を実施している。
《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、実施しているもの》
(24) 犯罪被害者等調査及び犯罪被害者等への対応の充実
法務省において、仮釈放等審理やそれに関連する調査、恩赦上申に際して、犯罪被害者等の感情の調査を行い、適切な仮釈放等の許否の決定や恩赦上申に努めている。
なお、仮釈放等審理を行うに当たり、「更生保護法」に基づき、犯罪被害者等から申出があったときは、その意見などを聴取している(P70(21)「犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放等審理の実施」参照)。

